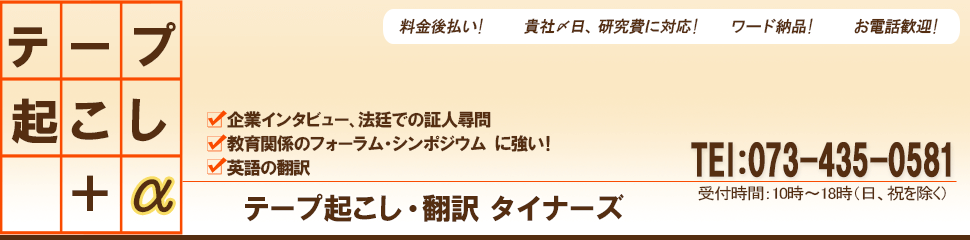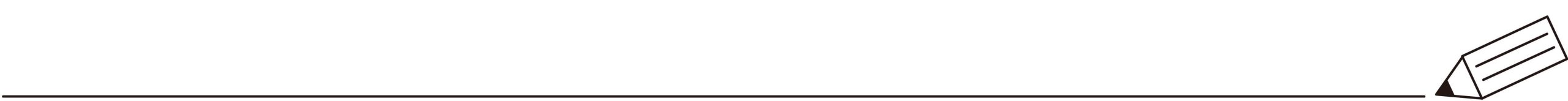2020/06/18

実際の会話とそれがテキストになった逐語録とでは、一つだけ差異があり、逐語録の使い方によってはコード化に影響を与えるのではないかと思っています。
その差異とは、ニュアンスです。
当社が長らく逐語録を作成している中で感じるのですが、沈黙も間(ま)も含めた、インタビューの発言通りすべて完璧に文章化した逐語録は、インタビュー音声とまったく同じであるかと言えば、まったく同じです。まるでインタビュー音声をテキストにコピーしたような感覚です。
ですが、どうしても、実際の発言(声)とテキストとを比べると、どうしてもテキストのほうが発言したニュアンスまでは見えづらい節があります。
たとえば、下記のインタビューイの発言を見てください。
==
それは、(間があく)そうですね。急性期医療の現場と後進の指導とをどのように両立させるかというのは、うーん、一つの課題で、(沈黙)そもそも慢性的な人不足が続く中で、誰がやるんだということはよく話に出てきます。
==
後段の「そもそも慢性的な人不足が続く中で、誰がやるんだということはよく話に出てきます。」について、
テキストで見る限りでは、少しため息が出ているような、「やれやれ、どうしよう」というような感情が伝わってきます。
しかし、実際はそうではなく、このインタビューイがとても快活な方で、ものすごく元気にこの発言をしていたとすると、どうでしょう?
なんとなく深刻な感じは薄くなったように思いませんか?
看護の枠から出て、ものすごく平易な例を出しますと、ケーキを食べたとき、すっごくローテンションの「このケーキおいしい」と、めちゃくちゃ元気に「このケーキおいしい!」というのとでは、前者は本当においしいと思っているのかどうか、テキストベースではわからないということですね。
テキストからは、このあたりの細かなニュアンスまで読み取ることが表すことができないんです。
このニュアンスの違いが、コード化の際に小さな影響を与える可能性が考えられます。
上記の例で言えば、インタビューイは深刻なこととして言っていると判断し、「急性期医療の現場での後進育成の懸念」というコードを付けたといます。でもじつはそんな深刻な言い方ではなく、あっけらかんと言っていたのであれば、案外、単にグチを言っているだけでコード化する箇所ではないという判断ができます。
であれば、逐語録(テキスト)にだけに頼るのではなく、収録したインタビュー音声も併用してニュアンスを確認しながらコード化を進めていくことで質の高い研究材料になります。
逐語録には、たとえば5分おきにタイムコードを振っておくなどすることで、何分何秒にどの発言があるかを探しやすく、便利です。
インタビュー 看護研究 逐語録の作成
https://www.osaka-p.com/tape/interview.html